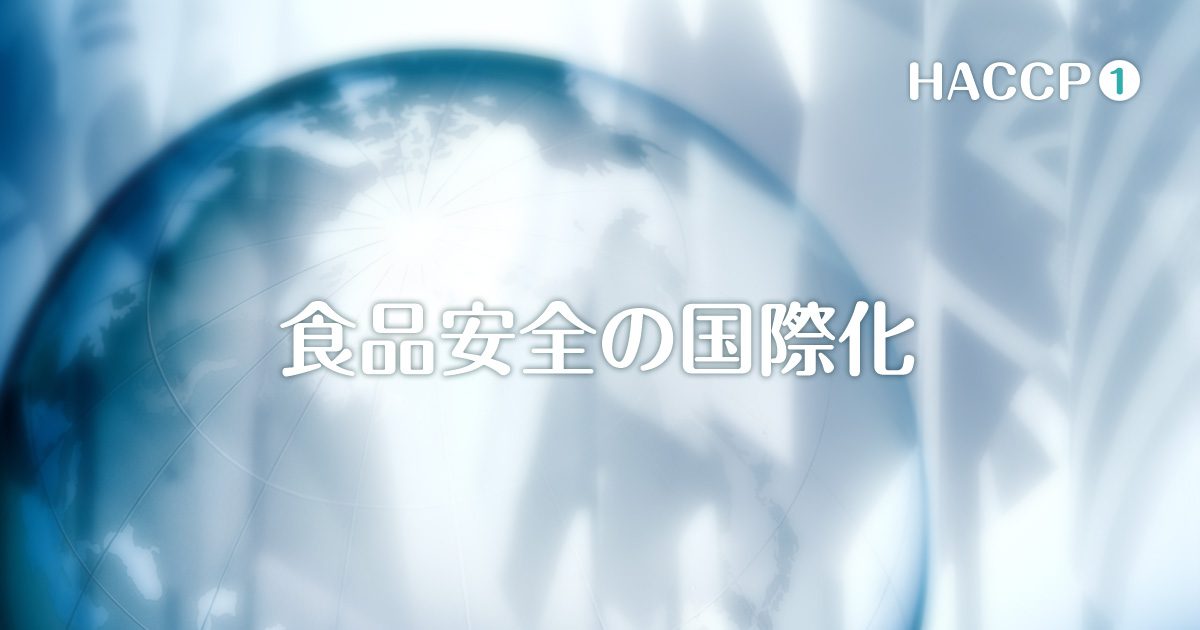
HACCPの制度化
HACCP(ハサップ)が制度化されました。
今、食品は国境を越えて流通しています。それは、どこでどのようにつくられた食品なのか分からない、という危険性があることを意味します。もちろん、それぞれの生産国でのルールがあり、また輸入する際には輸入国のルールがあり、それぞれのルールが守られているはずです。
でも、生産国と輸入国でルールが違う、という事態が生じます。それなら輸出する側は、相手国のルールを踏まえて生産しなければなりませんし、輸入国としても生産国のルールの違いが分かっていれば、輸入検査がしやすくなるでしょう。
HACCPの制度化は、国際化への対応です。日本における直接のきっかけは、2020年の東京オリンピック。オリンピックには海外から多数の観客が訪日することが見込まれますが、すでにアメリカ合衆国やEUなどではHACCPが義務付けられています。
これら海外から訪日する方々に対して食品の安全・安心を提供することは、最低限のおもてなしとなるのです。だからHACCPが制度化された、つまり義務付けられたのです。
ルールは国ごとに違うと言いましたが、実はHACCPは世界共通のルールなのです。
制度化されたからHACCPを導入するのか?
もちろん、義務付けられたのですから、HACCPを導入しないわけにはいきません。
でも、それだけでよいのでしょうか?
食品事業者の最大の使命は、お客様においしくて安全な食品を提供することです。それは「安心」の提供でもあるのですが、おそらく、「安心」はお客様以上に食品事業者が求めているのではないでしょうか?
万が一、食品事故が起こってしまったら、その対応が必要になり、状況によっては営業停止処分を受けます。それは金銭面でも重大な問題ですが、それ以上にお客様からの信頼を失うことになります。
「これまで食品事故が起きなかったのだから、これからも大丈夫だろう」とは限りません。なぜなら、食品事故を起こして営業停止処分を受けている事業者の大半は、これまで食品事故を起こしていなかったからです。
そもそも、HACCP制度化の目的は安全な食品の提供です。それは、全ての食品事業者が大切にしていることでもあるのです。
理解・納得して食品安全に取り組もう
食品の安全のためには、HACCPは効果的な手法です。でも、HACCPの認証を受けることだけを目的にしてしまうと、訳がわからないまま過剰な対応をしてしまうことにもなりかねません。
安全な食品を自信を持って提供するため、この連載でポイントを説明していきます。



